目次
須崎先生は、同じセミナーを何度も受講されるそうですが、それはなぜですか?
僕は、内容がわかっているセミナーを何度も受講するのは、お金も時間ももったいないと思うのですが…。
竹内さま
一生学びと実践・定着できているかの確認のため
私が今でもセミナーを受講しているというと、よく「えっ?」と言われるのですが、人生、死ぬまで勉強でございますので、私もしっかり学ばせていただいております。
そして「新しい情報なんてあるんですか?」ときかれるのですが、これだけ世の中が細分化されて深く研究されているわけですから、私が知らないことがあって当然で、むしろ学びを深めれば深めるほど知らないことが増えて来ます。
内容を知っているセミナーを再受講
竹内さんは私のセミナー受講生でいらっしゃいますでしょうか?おっしゃる通り、私には同じ講座を毎年再受講しているものがいくつかあります。
テキストは毎年変わらないので、内容はほぼ知っていることばかりです。スタッフの方々とも顔見知りで、中には「講師を目指されるのですか?」などと冗談を言われることもあります。
では、なぜその「知っていることばかりのセミナー」を須崎は毎年再受講しているのでしょうか?
この理由がわかると、「つまらないセミナー」とか、「コスパの悪いセミナー」というものが無くなります。
それは…
同じセミナーを再受講するメリット
「自分が習慣に出来ているかどうかをチェックするための機会」
「他人のペースで自分の人生設計を再構築するための機会」
と考えて参加しているのです。
この姿勢でいると、新しい情報があろうと無かろうとどうでもよく、「これは習慣化出来ている」、「これは習慣化できていないから、時間を確保しよう!」などとじっくりと考えられます。
一人で多数のプロジェクトを動かしていると、まとめてゆっくり考える時間が減ってきます。
そして、自分独りで事務所でそれをやろうとすると、スタッフの「ちょっといいですか?」とか、他のことが気になったり、やらなければならなかったことを思い出したりして、なかなか集中仕切れないのです。
誰にも邪魔されずに棚卸し→人生設計
そこで、誰にも邪魔されない環境に身を置き、セミナー講師のペースに沿って、棚卸しや復習、それまで気付かなかった視点などを織り交ぜて、今後のプランを練るのです。
そうすると、独りでは出来なかった様なプランが出来上がるのです。
私は、この効果をわかっているので、何度も繰り返し同じ様なセミナーを受講しています。
セミナー受講動機の段階
セミナー受講には、
- 新しい知識を得る段階
- その知識を日常生活で活用する段階
- その知識を習慣化する段階
- 無意識でその知識を活用できる段階
- 人に教えられる段階
があると思っています。
一回学んだくらいで習慣化できるならいいのですが、数日間のセミナー内容を全て、一発で、習慣化できる人などいません。
そんな人間ではないと自己評価しているので、繰り返し繰り返し学んでいるのです。
ですから、あなた様にも、シルバメソッドの再受講を「学び切れていないことを学びに行く」のはもちろんですが、自分の人生設計の時間として活用していただきたいのです。
この様に活用していただけると、「学ぶことはない」などということにはならないと思います。
一日千円程度で、人生設計のためのまとまった時間が取れるなんて、有意義だと思いませんか?
読書も同じ→無駄な本は無い!
実はこれは、読書活動もしかりです。
私は同じ様な内容の本をたくさん買います。
理由はいろいろあるのですが、その中の一つが、
「同じ内容を様々な表現で学べる」
というところにあります。
とえ話や、表現の仕方など、著者それぞれで異なるので、表現の幅が広がるのです。
表現の幅が広がる!
そうすると、この人にはこの表現で、あの方にはあの表現で、と変えることが出来るので、相手が腑に落ちていただける確率が増えていきます。
ですから、他人が「駄本」と評価した様な本でも、
「自分では思いつかない表現」を知ることも出来るし
「こう表現すると大多数の人はイラッとする」ことも学べます。
この様な姿勢で読書をすると、やはり「無駄な本」が無くなります。
知っているだけでは差はつかない!
何でもそうですが、
●知っていること
は別に偉くも何でも無く、ただ、早いか遅いかだけです。
しかし、その情報をどう活用するかは、その人次第です。
そして、この様に考えられると、「この本を買って失敗しないか?」などということも考えずに済みます。
学ぶ→対応可能領域が広がる→頼られる
そして、冒頭に戻りますが、より多数のお客様のニーズに応えられる様になれば、おひねりも増えますし、そのお金を自己投資に廻すことで、より多くのお客様の問題解決をすることが出来る様になり、さらにおひねりが増えるという、善の循環が生まれます。
これからは、知っているか否かではなく、問題を解決できるかどうか?そのぐらいに知識・情報を日常生活で実践・習慣化できているか?に焦点を合わせていきたいものです。
2045年問題に太刀打ちできる人材に!
2045年には人工知能が人間を超えるという話があります。
実際、チェスはコンピューターが世界王者に勝ちました。
「卓球ロボ」は、リアルタイムにボールの軌道を観察→計算して打ち返すことが出来る時代です。
人工知能が発達して、ロボットが人間に変わって仕事をする時代になると、人間の職が減ってくるという話もあります。
仮にそんなことになったとしても「余人を持って替えがたい存在」になっていれば、あなたにしか出来ないことで、世の中のお役に立てるはずです。
そんな「世の中に必要とされる人間」になるために、ぜひ、不断の努力を忘れず、そのための設計図をシルバメソッドのテクニックを使って描いていただきたいと思います。
私もまだまだ人生の半ばでございます。
共に刺激し合って、がんばりましょう!



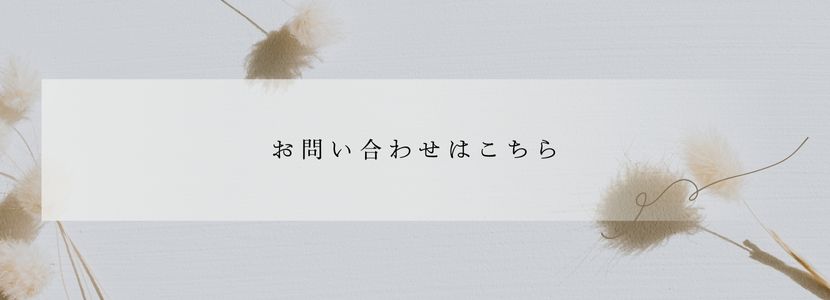







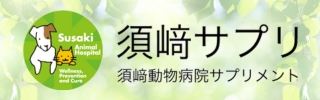




コメント